スマホで住民税・固定資産税を納税する手順|PayPay×SBI連携で5分完了
先月(2025年5月)退職し、これまで給与天引きだった住民税を、初めて自分で納税することになりました。

固定資産税は、今までも自ら納税してたから、それとおんなじ感じかな?
納付書はいつ届く?|住民税・固定資産税の支払い方法とタイミング
納税は、自宅へ納付書が届くことで気づきます。
予想どおり、住民税も固定資産税と似ていて、納付書は一括払いか、4回払いかを選べるようになっています。



固定資産税は5月に、住民税は6月に納付書が届いたわ。固定資産税は、自治体によって4月~6月と、届く月にバラつきがあるみたい。



ちなみに、退職が2カ月遅い7月やったら、当年度(6月~翌年5月)の住民税のうち、給与から引かれへんようになった分の納付書が送られてくるわ。ごましおは、たまたま新年度の納付から自分で納税するタイミングやったから6月やったけど、そうじゃないときは退職のタイミングになるはず。
それにしても、なんて便利な世の中なのでしょうか。
2020年頃までは郵便局で並んでいたのに、今はスマホだけで完了するんです。
この手軽さを知ってしまったら、もう以前の納税には戻れません。



みんな同時期に来るから、窓口が混んで時間かかってたのに、今やスマホで5分よ。
住民税も固定資産税も、どうせ払うもんです。
分割して毎回手続するのも面倒なので、一括払いにしました。



羽振りがいいわけではないで。固定資産税は毎月コツコツ積み立てしてて、住民税はあらかじめ計算して退職金から払う算段をつけてたのよ。



住民税は、シミュレーションサイトがあるから、『住民税 シミュレーション ○○市』とかで、出てくると思うで。
納税には、つぎのステップを踏みました。
PayPayと住信SBIネット銀行の連携が便利|目的別口座で納税準備もラクラク
なお、ごましおはpaypayにチャージする銀行として、住信SBIネット銀行を登録しています。



封筒開けたら、5分で納税♪



「玄関開けたら、2分でごはん♪」のリズムで読んでまうな。
目的別口座『退職金』から、住民税の金額を『代表口座』へ振り替えます



目的別口座名は、自分の好きな名称で10個作れるねん。
住民税の金額をチャージし、納付書のバーコードをスキャンして支払います
たった、コレだけです。おそらく、5分もかかりません。
スマホ納税のメリット・注意点|ポイント還元はある?
暑い日、寒い日、雨の日、どんなときでも、快適な自宅から納税できるんです。
めちゃくちゃ楽です。



ポイントつけへんのは残念やけど、満足。



paypayに銀行の登録もおすすめ。いつでも、どこからでもチャージできるから、めっちゃ便利。
住信SBIネット銀行の『目的別口座』をご存知ない方は、知らないと損しますから、ぜひこちらの記事でメリットを確認してみてください。





ただ、ドコモに買収されるから、操作性とか利便性とか、どうなんねやろ。便利な銀行やから、サービスが変わらへんか気になるわ。
住民税の一括徴収と退職金の関係|会社への申し出で納税をスムーズに
退職日が1月1日~5月末日だと、残っている住民税を退職金や退職月の給与で強制的に一括徴収されます。
ただし、退職金と退職月の給与の合計よりも、一括徴収する住民税の方が多い場合は、普通徴収となり、ご自身で納付しなければなりません。
退職月が6月1日~12月末日でも、当年度の残っている住民税を、退職金や退職月の給与で一括徴収してもらうことが出来ます。
一括徴収して欲しいときは、退職願いを提出した時点で、会社の給与担当者に申し出るのが良いでしょう。



任意で一括徴収してもらう時も、退職金と退職月の給与の合計額が、一括徴収する住民税より多くないと無理やで。
ところで、退職した翌年の住民税は負担が大きくて大変と、聞いたことはありませんか?
退職時に気をつけたいのは住民税だけじゃない|社会保険・給付制度もチェック!
退職後の健康保険はどう選ぶ?|国保・任意継続・扶養の違いを解説
日本の健康保険は、『国民皆保険』といって、生まれてから逝くまで、何らかの健康保険に加入しなければなりません。
健康保険にはどんな種類があって、どう選べばいいのかについての詳細を、こちらの記事で紹介しています。ぜひクリックして、ご覧ください。


離職票が届いたら何をする?|社会保険の切り替えと失業手当の準備
退職後は、住民税だけじゃなく、健康保険・年金・雇用保険といった社会保険の手続きも必要です。
健康保険だけでなく、年金や失業保険の切り替えも気になる方は、こちらの記事で詳しく解説しています。


教育訓練給付で給付制限を解除する方法|失業保険と学びの両立で生活費節約術
退職後の生活費が不安な方は、ハローワークへ行くのが早ければ早いほど、基本手当が支給されるのも早くなります。
なぜ、早く行くと基本手当の支給も早くなるのかは、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
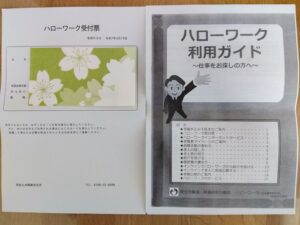
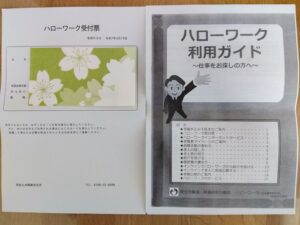
また、教育訓練給付の対象となる通信教育の受講で、失業保険の給付制限を解除し、生活費の節約につなげながら学ぶのもおすすめです。
失業保険を受給しながら学べる講座については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
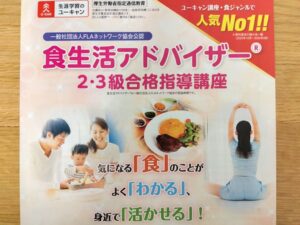
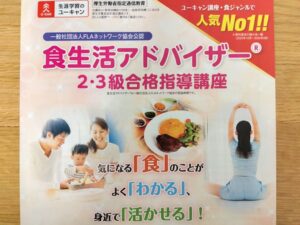
退職後の住民税はなぜ高い?|仕組みと納付タイミングを解説
住民税は、前年1年間の所得から計算されます。
サラリーマンは、勤め先の会社が、前年1年間のあなたの給与他を、当年1月にあなたが住んでいる市区町村へ報告しています。
給与収入以外に収入がある人は、当年の3月中頃までに確定申告を済ませます。
市区町村は、勤務先からの報告と確定申告を基に、年間の住民税額を計算します。
引き続き同じ会社で勤務している場合、市区町村は勤め先に、6月~翌年5月の給与で月割りした金額を徴収するよう連絡しています。



正しくは、12カ月で割ると端数が出るから、6月に端数処理して、7月~翌年5月は同額になるって感じやな。



ただ、扶養状況等に誤りがあったりと、場合によっては途中で金額が変わることもあるわ。
退職している場合、勤めていた会社は、あなたが住んでいる市区町村へ「退職したため、給与から徴収できません」と届け出しますから、自宅へ納付書が届くようになります。
当年に収入がなくても、住民税は、前年の所得から求められた金額を当年に納めることになりますから、退職すると住民税の負担は重いものとなります。



プロ野球選手とか、前年は年俸数億円やったけど、翌年ケガで契約切れて収入ゼロ…。それでも、前年の高収入分の住民税はしっかり請求される。そりゃ「ヤバい!」ってなるよな。



サラリーマンも、退職したら翌年の住民税は、前年の収入でしっかり請求されるからな。つぎの就職先が決まってないなら、注意せなあかんな。
給与から天引きされていると気づきませんが、住民税・所得税・社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険)と、負担額は大きなものです。



『租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率について公表します。令和6年度(実績見込み)45.8%』って財務相が出してるな。ごっつない?



租税負担率に、消費税も含まれてるらしいけど、それにしても負担でかいよな。
賢く節税しなければなりませんね。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
にほんブログ村ランキングに参加してます。

コメント