退職後に関係する社会保険の種類と仕組み|4つの保険と手続き
サラリーマンが支払う社会保険料は、4つあります。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
年齢や労働条件によって、加入する社会保険は異なります。
また、加入している保険料は、給料から控除されています。

辞めたら、それぞれで適切な手続きが要るからな。ここ、重要やで。
退職日の翌日から、健康保険や厚生年金に加入する労働条件で働く人は、以降の手続きは不要です。
それ以外の人は、速やかに手続きをしましょう。



退職後の手続きは、社会保険だけちゃうで。
住民税も、見落としがちなポイントですから、こちらの記事でまとめています。


健康保険・介護保険の切り替え手続きと選び方|退職後の加入方法と注意点
健康保険の選択肢|任意継続・国保・扶養の違いと判断基準
日本の健康保険は、『国民皆保険』といって、生まれてから逝くまで、何らかの健康保険に加入しなければなりません。
健康保険にはどんな種類があって、どう選べばいいのかについての詳細を、こちらの記事で紹介しています。ぜひクリックして、ご覧ください。





協会けんぽの人は、退職後に自分で手続きがせなアカンけど、マイナンバーカードとマイナポータルのアプリがあればオンラインで完結できるわ。それ以外の人は、在職中に会社の社会保険担当に相談しておくのがええで。つぎの健康保険にすぐ加入してないと、病気になったとき面倒やから。



3割負担で病院へかかれるところ、『いったん10割払って、後日申請して7割返してもらう』とかせなアカンようになるからな。健保は急ごう!
介護保険の加入条件と退職後の手続きの流れ|年齢別の対応方法
40歳以上の人が加入対象です。
健康保険に加入する働き方の、40歳以上65歳未満のサラリーマンであれば、自動的に加入となり、給与から控除されます。
しかし退職すると、任意継続健康保険料または国民健康保険料と併せて、徴収されます。
ただし、親族の健康保険の扶養に入ると、介護保険料は免除されることが多いです。
65歳以上になると、市区町村が管理するため、年金からの控除や個別納付に切り替わります。



健康保険の手続きと合わせて、40歳以上なら介護保険にも加入するで。ただし、親族の扶養に入る場合や、65歳以上の場合は、手続きの流れが変わるから要確認な。
厚生年金から国民年金への切り替え手続き|退職後の年金加入方法
退職後、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、基本的に国民年金へ加入します。
国民年金第1号の加入方法と必要書類|離職票と年金手帳の準備
手続きは、日本年金機構です。
退職日の分かるものと、基礎年金番号が分かるものを持参しましょう。



スマホとかパソコンがあれば、マイナポータルで電子申請もできるで。
退職日の分かるものの代表例は、ハローワークへ提出する、『離職票1』『離職票2』です。



退職手続きで、『離職票2』っていうのを確認させられるから、その時に、「離職票の送付を急いでほしい」って会社の担当者に頼むんがベストやで。
ハローワークへ提出してしまうと戻ってきませんので、提出する前にコピーを取っておくのが安心です。
基礎年金番号の分かるものの代表例は、『年金手帳』や、毎年誕生月におくられてくる、『ねんきん定期便』です。



idecoとか入ってる人は、『加入者被保険者種別変更届』も出さなあかんから、忘れんといてな。今は、「e-ideco」を使ってオンラインでも出来て便利になったわ。



保険料、納めんのが大変やったら、免除とか猶予の制度もあるから、日本年金機構で相談してな。ちなみに、免除したらidecoの加入資格はなくなるみたいやわ。そこも考慮して、検討してな。
国民年金第3号の加入条件と配偶者の手続き|扶養に入る場合の流れ
配偶者の健康保険の扶養に入る方は、配偶者の勤め先の担当者が加入手続きを進めてくれますから、そちらに相談してください。
雇用保険の申請方法|離職票と失業保険の流れ
失業中の生活を心配せずに、仕事探しに専念できるよう、『求職者給付』というものが雇用保険から支給されます。
求職者給付は、失業状態にある方のみ支給されるものですから、就職する気がなかったり、病気・妊娠・介護等で、いつでも就職できない状態だと支給されません。



「とりあえず辞めたし、失業保険でてる間はのんびりしよーっと♪」では、「働く気あらへんがな、それは失業状態とは言わん」って、ハローワークから言わるで。



積極的に仕事探してるのに就職できへんって状況じゃないと、あかんってことやからな。
求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を、『基本手当(通称:失業保険)』といい、この支給がすぐにでも欲しい方は、離職した会社から、『離職票1』『離職票2』が届き次第、すみやかにハローワークへ行きましょう。



退職の証明の代表格が、『離職票1』『離職票2』やから、ハローワークへ行く前に、コピーを取っておくのが安心やで。



ハローワークへ提出してしまったら、戻ってけーへんから注意してな。
退職後の生活費が不安な方は、ハローワークへ行くのが早ければ早いほど、基本手当が支給されるのも早くなります。
なぜ、早く行くと基本手当の支給も早くなるのかは、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
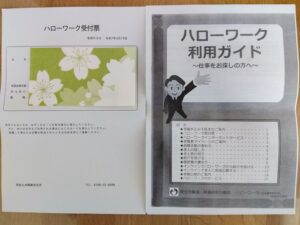
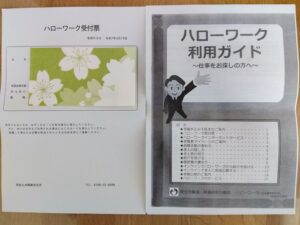
また、教育訓練給付の対象となる通信教育の受講で、失業保険の給付制限を解除し、生活費の節約につなげながら学ぶのもおすすめです。
失業保険を受給しながら学べる講座については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
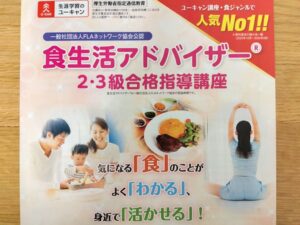
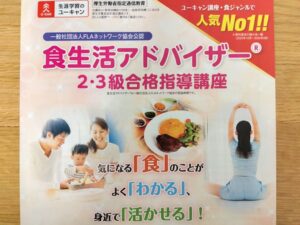
体験談|退職後の社会保険と失業保険のリアルな手続き記録



お待たせしました。ごましおのリアル体験談です。安心してください。ちゃんと失敗しますよ。



誰も待ってないし、不安でもない。
健康保険・介護保険の保険料比較と加入手続き|西宮市での実践記録
まず、退職後の選択肢は3つです。
- 任意継続保険
- 国民健康保険
- 親族の健康保険の扶養に入る
ごましおには、健康保険の扶養に入れる親族はいませんから、残る選択肢は2つです。
まずは、任意継続の保険料について、健康保険組合から月額保険料を教えてもらいました。
つぎに、国民健康保険料は西宮市の国民健康保険課へ電話し、月額保険料を教えてもらいました。
前年の収入が給与しかないのであれば、前年の源泉徴収票を手元に用意してから電話しましょう。



ごましおは、『令和6(2024)年分の源泉徴収票』を手元に用意してから、電話したで。
比較したところ、任意継続の方が安かったので、任意継続へ加入することに決めました。
そして、在職中に、『任意継続被保険者資格取得申請書』を、社会保険の担当者へ提出しておきました。
退職日の3日後には、健康保険組合から任意継続保険の払込取扱票や資格取得通知書が届きました。
なお、任意継続保険の払込取扱票には、介護保険料も含めての金額が載っています。



退職してから手続きしてたら、もっと遅なるもんな。



仮に退職日の10日後に来たとしても、その間に病院いきたいってなったら困るから、健保の手続きは在職中に動く方がええと思う。
2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず、マイナンバーを利用した『マイナ保険証』が基本となりました。
そのため、健康保険の加入状況を確認する際は、マイナポータルにログインして確認する流れになります。



ちゃんと『任意継続』で加入してたわ。マイナンバーカードって便利やな。



住民票とか印鑑証明を、コンビニで取れんのもええよな。
これで、健康保険と介護保険の手続きは終了です。
今年の11月には働かないと食べていけませんから、次は新しい会社の健康保険に入ることになるでしょう。



忘れてたけど、おまんま食い上げのピンチやったわ!でもピンチはチャンスやから!



この場合、ピンチはピンチじゃない?ま、なんとかなるか。
離職票の取得と年金切り替えのタイミング|国民年金第1号への移行手順
国民年金第1号被保険者へ切り替え
ごましおの退職後の選択肢は、国民年金に加入するしかありませんでした。
事前の問い合わせで、手続きに必要なものは下の2点と言われていました。
- 退職の事実のわかるもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
退職の事実のわかるもの代表格は、ハローワークへ提出する、『離職票1』『離職票2』です。
基礎年金番号のわかる代表格は、『年金手帳』『ねんきん定期便』です。
ごましおは、離職票が届いた日に念のため離職票のコピーを取ってから、年金手帳を持って年金事務所へ行きました。



「離職票の送付を急いでほしい」と退職手続き時に、お願いしてただけあって、退職日の1週間後には届いたな。



忙しいのにありがとー!
年金事務所には、15時過ぎに到着しました。
受付で、「退職したため、厚生年金から国民年金へ切り替えたい」と申し出たところ、番号札と記入用紙を渡されました。



名前と住所と電話番号と相談内容を書くような用紙やったけど、渡された瞬間、「これ要るか?」って思ったな。
仕方がないので記入していたら、書き終わった瞬間に呼ばれました。



なんやねん。書き終わんの待ってるやん。手には年金手帳持ってるし、用紙じゃまやし、ボールペンも地味に鬱陶しいし、もうワチャワチャするわ。
なんとか立ち上がり、ひょこひょこ窓口まで歩いて行って、用紙を担当者へ渡します。
担当者は用紙を受け取りますが、見るでもなしに視線を合わせてきます。



なんで書かせてん。ぜったい要らんやろ。
仕方がないので、何をしに来たかを口頭で説明すると、1枚の用紙が手渡されました。
さっきも書いた名前と住所と電話番号を、また書かなければいけません。



おんなじことばっかり書かせやがって!やっぱりさっきの用紙、要らんやないか!
資格取得日の記入になると、担当者が日付を言ってきます。



え?ま、合ってるけど、もう知ってるん?
「退職日って、もう分かってるんですか?」
「会社さんが、もう提出されてるんで」
そういえば、会社も電子申請で資格喪失届をだしています。
さすが電子申請、すばらしいスピードです。
あっという間に手続きは終わり、用紙を持っていかれそうになります。



いや、ちょっと待って!『付加年金』っていう、恐ろしく割のいい年金も入りたいねん!
付加年金にも加入
付加年金は、国民年金第1号被保険者だけが加入できる制度で、月額400円で加入できます。
将来、受け取れる年金の年額は、『200円×納付月数』となります。
仮に半年間、付加年金に加入したら、『400円×6カ月=2,400円』の保険料を納付することになります。
2,400円の納付で将来、毎年1,200円受け取れることとなります。※200円×6カ月=1,200円



この計算式やったら、2年で元とれるやん!67歳超えたら、超えた分だけ得やもんな。



物価スライドがないから、『インフレの影響を受ける』とか、『65歳までに逝ってもうたら払い損』とかあるけど、それでも割のええ制度やな。
慌てて、「付加年金にも入りたい」と申し出て、無事、付加年金にも加入することができました。
支払いは納付書・口座振替・クレジットカード・スマホアプリ・ねんきんネットと、いろいろありました。
クレジットカード払いならポイントも付くし、手間がかからないと思い、カード払いにしました。
これで仕事は終わったかと思ったのですが、担当者が追加の説明を始めます。
「クレジットの引き落としには数カ月かかりますから、最初は納付書で支払ってください」
「…はい」



え?なにそれ。最初にゆってよー。クレジットで引き落とし始まったの分からんで、納付書でも払ってまうかもしれんやん。



どうせ長くて半年なんやから、それやったらカード払いじゃなく、納付書払いでよかったのにー。もー。
今さら手続きを変更するのも面倒ですし、ちょこっととはいえ、ポイントも付きます。
なんとか自分を納得させたのですが、衝撃の事実が発覚しました。



しもたー!指定したクレジットカードは、ポイント付けへんタイプやん!
どうやら、ポイントが『付くカード』と『付かないカード』があるようです。
さらに、カードの有効期限が到来した時には、再度手続きが『必要になるカード』と『ならないカード』があるようです。



1年後の5月にカードの有効期限きれるな。それまでに働かなな。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の種別変更届の提出
SBI証券でイデコに加入していたため、SBI証券のイデコサイトから、『加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)』を、2025年3月に取り寄せました。
退職日まであと2カ月ほどありましたが、退職日の変更はありません。
忘れると面倒なので、送付されてきた変更届に必要事項を記載し、すぐさま投函しました。



変更年月日は、退職日の翌日やで。
しばらくすると、「平素は…誠にありがとうございます。以下の不備が…」という丁寧な文書とともに、返却されてきました。



簡潔に言うと、「退職してから出してこんかい、わーれー」やな。
同じ失敗を繰り返してはいけないので、日本年金機構で第1号被保険者への切り替え手続きを終えてから、再度、投函しました。



今度こそ、何事もなく受理されますように!えらい、すんまへんでした!
雇用保険の申請手順とハローワークでの流れ|持参品と認定日の注意点
雇用保険は、健康保険・介護保険・年金保険とは異なり、無職のときは加入しません。
では、何をしにハローワークへ行くのかというと、雇用保険の基本手当(通称:失業保険)をもらいに行くのです。



とにかく早くハローワークへ行くんが大切。離職票出さんことには、話ならんで。
持参品
- 離職票1、離職票2
- 失業保険を振り込んでもらう銀行のキャッシュカード
- マイナンバーカード
- 給付制限解除に係る証明書



証明写真って、1,000円超えるって知ってた?案内文には、『証明写真2枚』ってあったけど、毎回マイナンバーカードを提示するなら省略可ってあったから、持っていかへんかった。



1,000円超え?!いつの間に。400円くらいのイメージやってんけどな。
ハローワークは、とにかく待ち時間が長いです。



本とかスマホとかで時間潰すけど、番号札で呼ばれるから、いまいち集中できへん。



フードコードみたいに、ブザー渡してほしいわ。
ユーキャンを受講し、『給付制限解除に係る証明書』を提出したので、待期期間7日を過ぎれば、失業保険の支給が開始されるようになりました。
退職1週間後にハローワークへ行ったおかげで、翌月の末くらいには、最初の失業保険が振り込まれそうです。



よーし。いい感じ。
今後のスケジュールとしては、『雇用保険説明会』なるものに出席します。
それ以降は、4週間に1回の決められた、『認定日』にハローワークへ出向き、失業状態を認めてもらうことになります。
認定日に認められてから、約1週間で失業保険が振り込まれますが、行けばいいってもんじゃないそうです。
しっかり求職活動をしたという実績を、申告しなければなりません。



ハローワークの人に職業相談したり、セミナーに参加したり、求人に応募したりするらしいわ。



どしよかな。何しよかな。あと5カ月しかないな。あっという間やな。
「こんな風に仕事探すと良いよ」という意見をお持ちの方、ぜひともアドバイスをお願いいたします。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
にほんブログ村ランキングに参加してます。

コメント